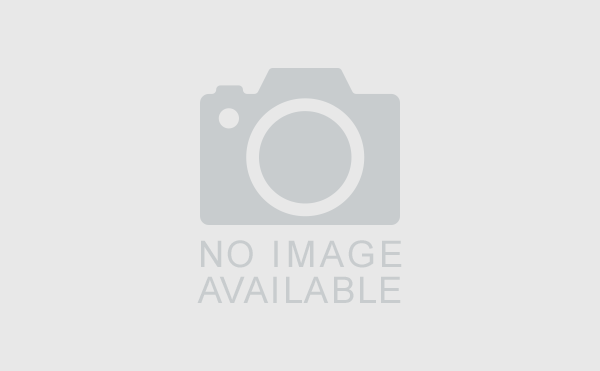介護保険が危ない
介護人材の不足や、介護事業者の倒産が続くなど、2000年に始まった介護保険は、超高齢社会おいて今後が心配されています。
1月18日東京生活クラブの企画による大熊由紀子さんの高齢福祉の歴史や課題を伺った。大熊さんは朝日新聞の科学部の記者だった。
特別養護老人ホームは、1963年に老人福祉法を根拠として始まった。79年に、2000年には寝たきり老人が100万になるとして日本型福祉が始まった。男性学者政治家行政官は、福祉予算を倹約するために、拘束や床ずれを招くベッドに寝かす形のことで、結果として医療費も膨らんだという。また、家族が介護をすることが前提となったことも日本型と言える。
一方デンマークなどではホームヘルパーの処遇もきちんとしており、療養型をなくして、認知などがあっても生かされた機能を引き出し(自己資源バスケット)ケア付き住宅に住みながらケアされる。そのため尊厳が保たれ改善されるケースも多いという。
1990年ゴールドプランで、ホームヘルパー10万人と寝たきりを0を目指すことになった。そして2000年から始まった介護保険につながるが、94年高齢者介護自立支援システム研究会で検討、自さ社政権で現在の原型がスタートしたのだそうだ。自民党政権では根強い家族介護論があり、政治がかかわる役割の大きさを実感した。
認知症で精神病院に入るようになったのは、空きベッドを使うことで赤字を解消するための極めて政治的な動きときいて驚いた。そして、徘徊をすることを前提にしているので病院には長い廊下になっている(回廊式)のだそうだ。北欧の風景とは全く違う。
しかし、認知症対策としてオレンジプランでが策定され、できる限り地域の良い環境で自分らしく暮らし続けることができることを目指すようになっているとのこと。
ところが、介護保険改定で、要支援1・2が保険から切り離され自治体任の総合事業となり自治体任せになっているが、次期改正案では介護度1・2も適用させ、ケアマネージャーの自費負担を導入しようとしている。介護離職が懸念され、介護保険でカバーしてきた認知症なので大きな矛盾がある。市民とともに声を上げなくてはならない。